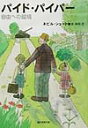小さな頃に読んだハーメルンの笛吹きは怖かった。ペストの蔓延に苦しんでいた中世の欧州で隔離政策が取られていることの比喩であるという説を読んだのはマスターキートンだったか。
街から消えていく子どもたちと、とり残される大人たち、それは希望が消えて絶望しか残っていない街を表しているようで、とても怖かったのである。
この本に出てくる大人たちは自らは抜け出せない状況に苦しみながらも、子どもたちをハワードに託す。希望を未来に託すように。
懺悔や後悔を抱えた旅だと思った。主人公の老人 ハワードは静養に訪れていたフランスで第二次大戦の激化に伴い、知人の子ども二人をイギリスに連れていくことを頼まれる。彼は自身の息子を戦争で亡くしている。
老年に達している主人公は既に戦場に行くことも、町場でそのための支援をすることも出来ず倦んだ気持ちを抱えていた。
無理な頼みに戸惑いながらも子どもたちを連れてイギリスを目指す旅に出たのは、深刻度が増す戦況の中で自分に出来ることがあったのを見つけた喜びがあったからではなかったか。
通りすがりの街々で人々に救われながら、子どもだけでもと縋られ、徐々に連れ立つ子どもたちは増えていく。
まだ小さく意味もわからず爆撃機に憧れる子ども。子どもながらに子守の上手い子ども。爆撃で両親を亡くし感情を失ってしまった子ども。迫害の対象になっていた子ども。ナチスを憎みドイツ人を殺すと息巻く子ども。
三蔵法師が天竺を目指すような、遠い世界を目指す殉教の旅のようである。しかし命を落とすことはそのまま子どもたちを損なうことを意味する。泥水をすすっても絶対死なないと誓う、死ぬより厳しいかもしれない殉教である。
イギリス人ににとっても、フランス人にとっても、ドイツ人にとっても、アメリカ人にとっても、子どもたちは希望だったのだ。子どもたちを連れて進んでいく年老いたパイドパイパーは希望の光に照らされていた。